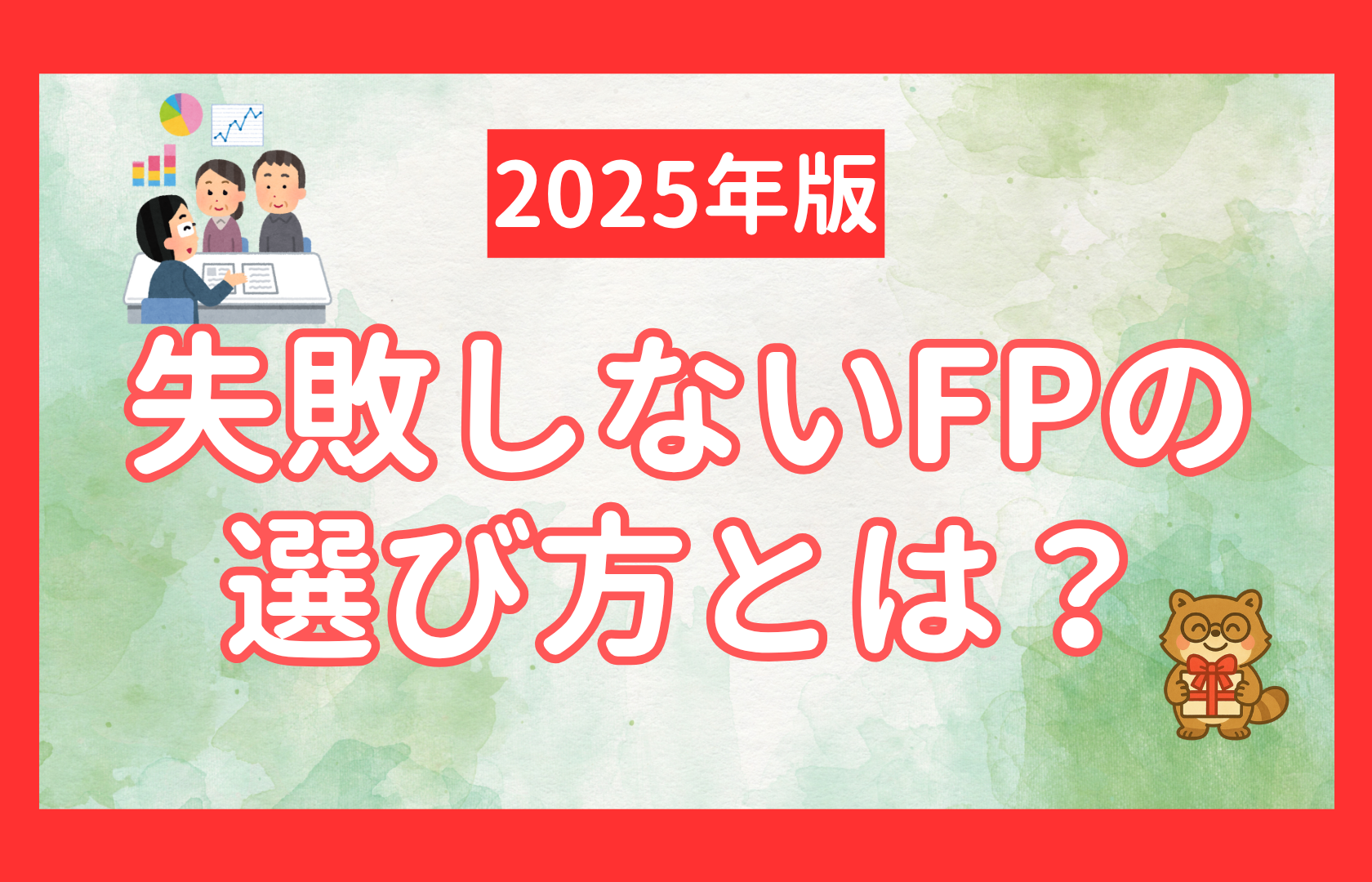【完全比較】NISAとiDeCoの違いとは?投資初心者が選ぶべき制度はどっちか
NISA・iDeCo

「NISAとiDeCoってよく聞くけど、正直どっちを始めればいいのかわからない…」
そんな風に感じている投資初心者の方は多いのではないでしょうか。
税金の優遇がある制度とは聞くものの、仕組みや制限が複雑で、なんとなく手を出しづらい。
そして気づけば「調べるだけで疲れて結局何も始めていない」なんてことも。
でも大丈夫。この記事を読むことで、あなたに合った制度が明確になり、最初の一歩がスムーズに踏み出せます。
今回は、「NISAとiDeCoの違い」をわかりやすく解説しながら、どちらを選ぶべきか、どう選べばいいかの判断ポイントまで丁寧に紹介します。
目次
NISA・iDeCoとは?まずは基本の仕組みを整理

NISA(少額投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)は、どちらも税金の優遇を受けられる制度です。
ただし、その目的や使い方は大きく異なります。
【NISAの特徴】
- 投資で得た利益(売却益・配当)が非課税
- 資金の出し入れが自由
- 目的は「資産形成」や「運用体験」
- 新NISAは年間360万円まで投資可能(成長投資枠240万+つみたて投資枠120万)
【iDeCoの特徴】
- 掛金が全額所得控除になる(=所得税・住民税の節税に)
- 原則60歳まで引き出せない
- 目的は「老後資金の準備」
- 上限は月額12,000〜68,000円(職業・勤務形態による)
違いを比較!NISAとiDeCoの違いを表でまとめ
| 比較項目 | NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 税制メリット | 運用益・配当が非課税 | 掛金が全額所得控除+運用益も非課税 |
| 引き出し自由度 | いつでも引き出せる | 60歳まで原則引き出し不可 |
| 資金拘束の有無 | 拘束なし | 拘束あり |
| 投資上限額 | 年間360万円(新NISA) | 月額1.2〜6.8万円(年14.4〜81.6万円) |
| 対象者 | 日本国内に住む18歳以上の人 | 原則20歳〜60歳の国民年金加入者 |
| 目的 | 中長期的な資産形成 | 老後資金準備 |
どっちが自分に合ってる?判断ポイントを解説
【NISAが向いている人】
・いつでもお金を引き出したい
・家・教育・旅行など幅広い目的で使いたい
・とりあえず投資を体験してみたい
・所得が少なく、控除の恩恵があまりない
【iDeCoが向いている人】
・節税したい(所得税・住民税を減らしたい)
・60歳までお金を動かす予定がない
・老後資金を着実に積み立てたい
・安定収入があり、節税メリットが大きい
節税効果を年収別にシミュレーション

【iDeCoの例】
年収500万円の会社員が、月2万円をiDeCoに拠出すると…
→ 年間24万円の所得控除
→ 年間の節税効果:約4.8万円〜6万円
【NISAの例】
年利5%で年間20万円の運用益が出た場合
→ 通常なら約4万円の税金が非課税に
→ 手取りでまるごと20万円が残る
失敗しない銘柄選び3つのコツ
- 目的別に分ける→ NISA:中期資産形成、iDeCo:長期・年金代替
- リスクを抑えて長期運用→ インデックスファンド、バランス型が◎
- 手数料の安い商品を選ぶ→ 信託報酬0.2%以下を目安に選定
体験談|NISAとiDeCoを併用して安心の資産形成に
30代女性・会社員
「iDeCoを先に始めて、将来の年金対策に。
その後、NISAも始めて日常用の資産も同時に作れるようにしました。
今では両方合わせて月5万円。
節税にもなるし、投資の知識も自然と身について、自信がついてきました!」
投資初心者がやりがちな失敗と対策
・高リスク商品に一括投資
→ 初心者は分散&積立を意識!
・積立が続かない
→ 自動積立設定+通知アプリで継続しやすく
・情報収集で疲れる
→ まずはSBI証券や楽天証券の人気ランキングから始めるのも手
【Q&A】NISA・iDeCoのよくある疑問に回答
Q:NISAとiDeCo、両方同時にできるの?
A:はい、可能です。目的別に使い分けましょう。
Q:iDeCoって途中でやめられる?
A:積立は止められますが、原則60歳まで引き出せません。
Q:証券会社はどこがいいの?
A:SBI証券、楽天証券など、手数料が安くアプリも使いやすいネット証券がおすすめです。
まとめ|目的で選べば投資の第一歩がスムーズに
NISAとiDeCoは、どちらも優れた制度です。
- 柔軟に使える資産が必要 → NISA
- 老後資金+節税目的 → iDeCo
両方を併用することで、短期・長期のバランスも取れます。
まずは自分の目的を明確にして、
少額でもいいので「今日から投資」を始めてみましょう。
Related posts